blog»ブランド・マーケティング»AIは誰が使いこなすのか?これからの時代に求められる人材とは
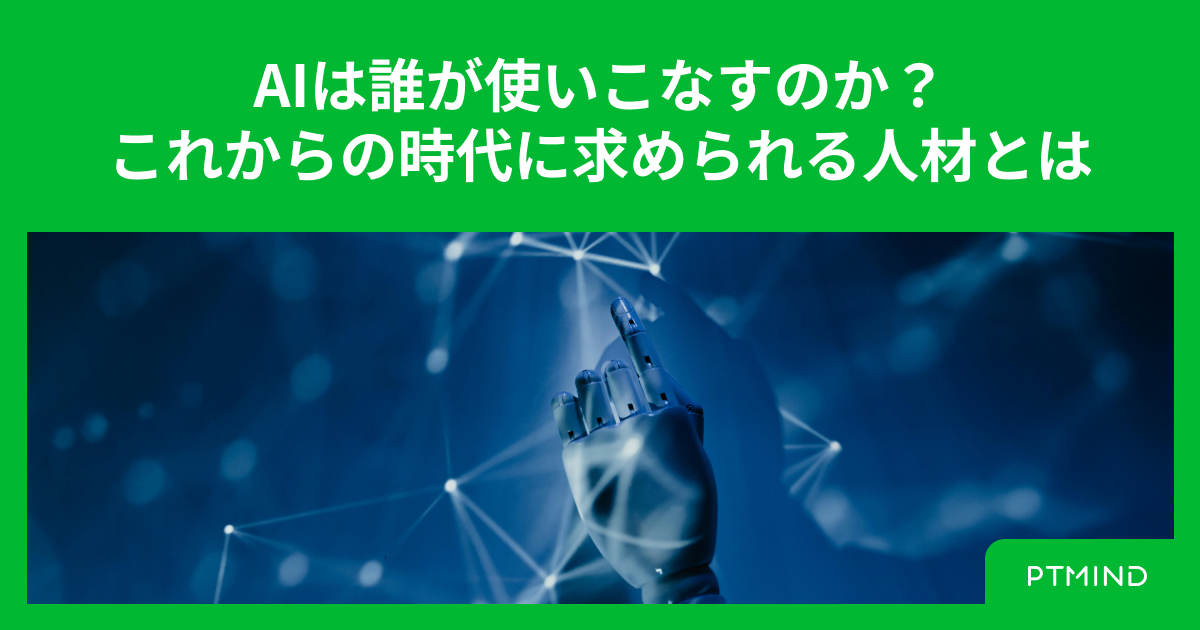
AIは誰が使いこなすのか?これからの時代に求められる人材とは
2025年08月18日
この記事は約8分で読めます。
はじめに:AIは「使いこなす人」で差がつく時代に
生成AIの急速な進化により、誰でも簡単に高機能なツールを扱える時代が到来しました。しかし、ただAIを使えば成果が出るわけではありません。重要なのは、AIに何をさせるかを考え、その出力を活かせる人材かどうかです。
McKinsey & Companyの調査によると、92%の企業が今後3年間でAIへの投資を拡大すると回答しており、多くの企業が生成AIの導入に前向きな姿勢を示しています。 しかしその一方で、AIを「本格的に使いこなせている」と答えた企業は、わずか1%にとどまっています。
このように、多くの企業がAIを導入しているにもかかわらず、期待した効果を感じられなかったり、現場で定着していないという声も少なくありません。 その背景には、「問いの立て方」や「活用スキルの不足」といった課題が横たわっています。
本記事では、AI時代に求められる人材像やスキル、企業が取るべき育成アプローチについて、具体的な事例やリスクとともに解説します。 AIの力を“現実の成果”につなげるために、いま何が必要なのかを、ぜひ一緒に考えていきましょう。
「問いを磨く力」がAI時代のコアスキルに

AIを上手に活用できる人は、単にツールの使い方を知っている人ではなく、「AIにどんな質問をするのか」「その答えをどう評価するか」といった質問力を持つ人材と言われています。
【なぜ質問力+判断力が重要なのか?】
- AIの答えは「確率的な予測にすぎず」常に正しいとは限らない
▶︎自信たっぷりでも間違っていること(=ハルシネーション)がおこるリスクがあるから - 複数のAIツールを経由すると、誤情報が拡散・増幅されるリスクがあるから
- AIは偏りのある情報や視点を反映する可能性があるから
- 時間が経つと情報が古くなるため、「これは今も正しいのか?」「どの情報ソースを参照しているのか?」と見直す必要があるから
AI時代における「優れた問い」とは?
AI活用で成果を出すには、「どんな問いを立てるか」「その答えをどう扱うか」がカギになります。
AIを上手く活用するには、「問いの質」が何よりも重要です。ただ便利なツールとして使うのではなく、思考を深め、課題を構造化する問いを立てられるかが成果を左右します。以下のような場面で、問いの違いがどのように結果を変えるかを見てみましょう。
例1:広告の効果が頭打ちになっているとき
- ❌ 悪い問い:「なぜ広告の成果が出ないのか?」
- ✅ 良い問い:「広告成果に影響している要因は何か?(ターゲティング、クリエイティブ、媒体、時期など)」
▶︎ ポイント: 結果の背後にある構成要素に目を向け、分解することで改善アクションが明確になります。
例2:新たなコンテンツ企画を考えるとき
- ❌ 悪い問い:「何かバズる企画はないか?」
- ✅ 良い問い:「ターゲットが今抱えている悩みや欲求は何か?それに応える切り口はどうか?」
▶︎ ポイント: 表層的な流行ではなく、「誰のどんな課題を解決するか」に立脚した問いが、価値のある企画を生み出します。
例3:メルマガやCRM施策の効果が弱いとき
- ❌ 悪い問い:「なぜメールを開いてくれないのか?」
- ✅ 良い問い:「どのセグメントの顧客に、どんなタイミング・内容でアプローチすれば最も効果的か?」
▶︎ ポイント:データを起点にしながら、ユーザーの行動や関心に沿って仮説を立てていくことが重要です。
「なぜ成果が出ないのか?」といった漠然とした問いではなく、「どの要因が成果に影響しているか?」「誰に・いつ・何を届けるべきか?」のように、仮説を含んだ具体的な問いを立てることで、AIは実用的な示唆を返してくれます。
AIはあくまで補助ツール。良い問いが、良い答えを引き出す鍵です。
そのため、AI人材育成においては、プロンプトの型を教えるだけでなく、「なぜその問いをするのか」「どう答えを評価するのか」といった思考のプロセスを鍛えることが、これからの競争力につながります。
AIの“盲点”─誤情報と偏見を増幅する仕組み
AI同士が生む「誤情報の連鎖」
AIの答えは常に“もっともらしい”推測にすぎないということを念頭に置いてお考えることが重要です。いかに精巧なモデルであっても、確実な正解を出しているわけではなく、誤った内容をあたかも正確な情報のように語ることもあります。
さらに懸念されるのは、複数のAIツールを組み合わせたときの「誤りの増幅」です。たとえそれぞれのツールが95%の精度を持っていても、5つ連携させると全体の信頼性は78%程度まで低下します。

実際、多くのAIが生成したコンテンツがインターネット上で共有・再利用され、別のAIに取り込まれるという循環が生まれています。AIが作った情報を別のAIが再利用することで、誤情報や偏見が何度も増幅・拡散されてしまう現象、「AIのエコーチェンバー化」が進行しており、これが誤りを何重にも強化する要因となっています。
また、「正確さ」と「質の高さ」は別の問題であることを忘れてはいけません。AIは不正確な情報でも、それをきれいに、説得力をもって繰り返すことができます。したがって、AIの回答は鵜呑みにせず、その背後にある情報源を自分で確認することが必要です。特に医療、法務、金融などの分野では、人間の専門家によるファクトチェックが欠かせません。
AIは公正ではない ― バイアスの正体とは?
生成AIと会話をしているとあたかも、ある一人の人間と会話しているように感じてしまいますが、実際には人間のような意識や判断は持っていません。しかし、AIにも人間らしい偏りが現れることがあります。
これは、AIがどのようなデータで訓練され、誰によって設計されたかに大きく依存しているため、AIにも人間のようなバイアスがあると言われています。

たとえば、2024年にワシントン大学が行った研究では、大規模言語モデルを用いた履歴書スクリーニングAIが、白人男性の名前を持つ応募者を優遇し、黒人男性の名前を持つ履歴書を一度も1位にランク付けしなかったという結果が示されました。
アジア系女性の名前は若干高い順位になる傾向がありましたが、全体としてこのAIは、採用のプロセスにおける歴史的な人種差別が反映されていたことがわかっています。このように、訓練データにバイアスがあると、AIも同様にバイアスのかかった判断をするということが研究で証明されています。
バイアスが生まれる仕組みを理解する
AIにバイアスが生まれる背景には、学習に用いられるデータの偏りや設計者の意図が深く関わっています。たとえば、過去の採用データや社会の既存の不平等が反映されたデータを用いると、AIはそれをそのまま学習し、不公平な判断を下すことがあります。
つまり、AIの判断は「中立」ではなく、あくまで学習元となる情報の性質に大きく依存しているため、この仕組みを理解することが重要です。そのため、AIを訓練する際にもとデータの多様性や公平性を意識し、トレーニング前に偏りをチェックする取り組みが欠かせません。
最終判断は人間であるべき
一方で、AIの判断にすべてを任せることは避けるべきです。特に採用や医療、法務など、人の人生や権利に大きく影響する領域では、AIの出した結果を鵜呑みにせず、人間の判断を介在させる仕組みが必要です。
AIはあくまで補助的なツールであり、最終的な意思決定には人の倫理観や状況把握力が不可欠です。AIと人間が適切に役割分担し、それぞれの強みを活かすことで、公平で責任ある判断を実現できます。
AI人材をどう育てるか:企業が取るべき育成アプローチ
現場業務にAIを「埋め込む」:日常的に触れる仕組みを
AIを特別なものにせず、業務の一部として「当たり前」にする環境づくりが効果的です。
- 例:マーケティングでの広告文・タイトルのA/BテストBテスト案出し
- AIが複数の広告案を作成し、過去のデータから効果が期待できるパターンを抽出。担当者は実施プランを決定。
- 目的: キャンペーンごとの繰り返し業務でAI活用を定着させ、広告効果の最大化を図る。
- メリット:AIを日常業務に繰り返し組み込むことで、現場の自然な活用習慣が生まれ、スキルや成果の定着につながります。
AIの使い方を学ぶだけではなく質問力、判断力を磨く研修を行う
AIの操作方法を教えるだけでは、業務への応用力は高まりません。特に生成AIでは、問い方ひとつでアウトプットの質が大きく変わるため、「良い問い」を立てる力が不可欠です。同時に、その答えをどう読み解き、どう活かすかといった判断力や批判的思考力も必要です。
- 例 :
- ChatGPTに「化粧品業界トレンドをようやくして」といったプロンプトで問いかける
- 出てきた情報の信頼性をチームで検証(事実確認・引用チェック)
- 間違っていた部分を特定し、「どの聞き方をすれば誤情報を減らせるか」を検討
- 目的:
- 「AIは常に正しいとは限らない」ことを体験ベースで理解
- 出力の検証・ファクトチェックの重要性と方法を学ぶ
- 情報の質を見る目を養う(特に医療・金融・法務など信頼性が問われる領域向け
- メリット:AIの出力を検証するプロセスを実践することで、情報リテラシーが高まり、AIに依存しすぎず適切に活用できる判断力が養われます。
自発的な学習を促すインセンティブ設計
AI分野は変化が激しく、継続的な学びが不可欠です。そのため、社員が前向きに学び続けられる仕組みが重要です。
- 例:
- 社内でのAI資格取得に対する報奨金や表彰
- AI活用スキルを業績評価に組み込む
- 学習の成果を共有・見える化する機会(ピアレビュー、ライティングトーク会など)
- 目的:学ぶことが「面倒な義務」ではなく、「成果につながる価値」と認識されるようにする
- メリット:インセンティブを設けることで、社員の自発的な学習意欲を高め、AI活用スキルの定着と組織全体のスキル底上げを加速させる効果があります。
AIで「教える」:個別化・継続的なスキルアップ支援
AIそのものを学習サポーターとして活用する方法も注目されています。
- 例:
- 社内GPTによる業務ナレッジのFAQ対応
- トレーニングチャットボットでプロンプトの練習やフィードバック
- 目的:個々のレベルや関心に応じた学びを、いつでも・自分のペースで行えるようにする
- メリット:忙しい現場でも“短時間×高密度”でスキルアップが可能です
終わりに:AIを成果につなげるのは、人間の問いと思考力
AIが高度になればなるほど、それをどう使うかは人間次第です。生成AIはあくまで補助ツールであり、そこから価値を引き出せるかどうかは、「問いを立てる力」「活用の判断力」「思考のプロセス」が非常に重要になってきます。
今後、どの企業もAIを導入するのが当たり前になっていく中で、差を生むのはAIを「使える人材」がどれだけいるかという点です。そのためには、単なるスキル習得にとどまらず、日常業務にAIを溶け込ませ、自発的な学びと実践を促す仕組みが重要になります。
AIに振り回されるのではなく、自分の目的に合わせて賢く使いこなす。そんな「人間ならではの力」が、これからのAI時代の本当の競争力になるはずです。
参考文献
- 10 Real-Life AI in Marketing Examples and Use Cases, smartosc
- Bias in AI: Examples and 6 Ways to Fix it in 2025, AI Multiple
- AI Will Shape the Future of Marketing, Harvard University
- Superagency in the workplace: Empowering people to unlock AI’s full potential, McKinsey & Company
- AI人材とは?不足している理由や人材の育て方, primagest
- AI人材が必要な理由やAI人材育成の方法について解説, NTT ExC パートナー